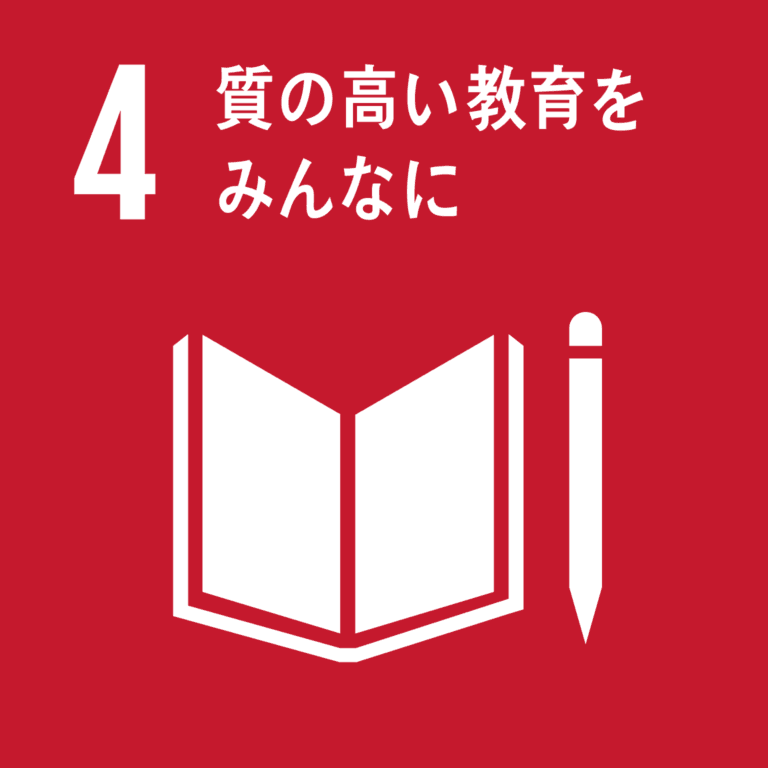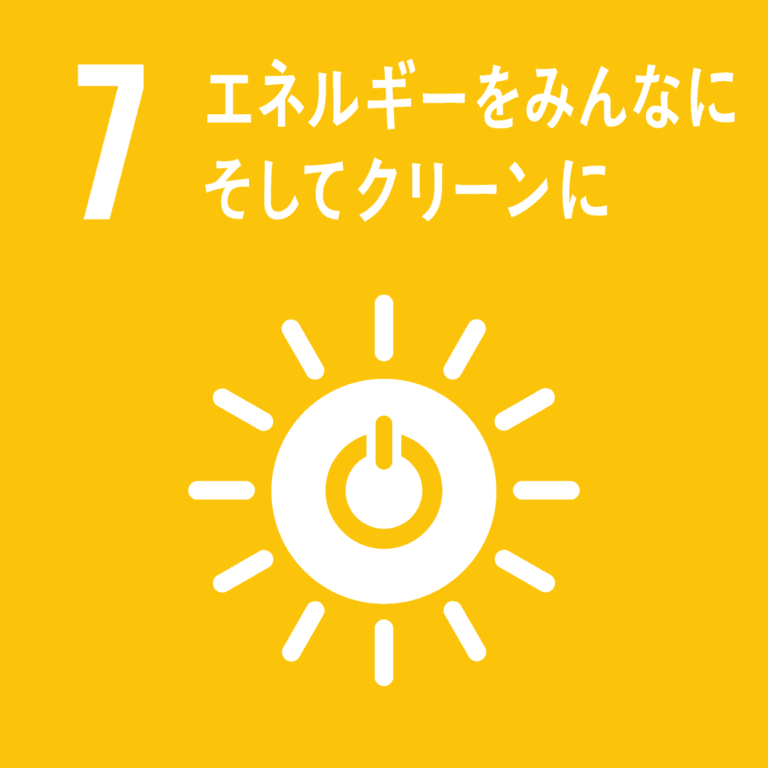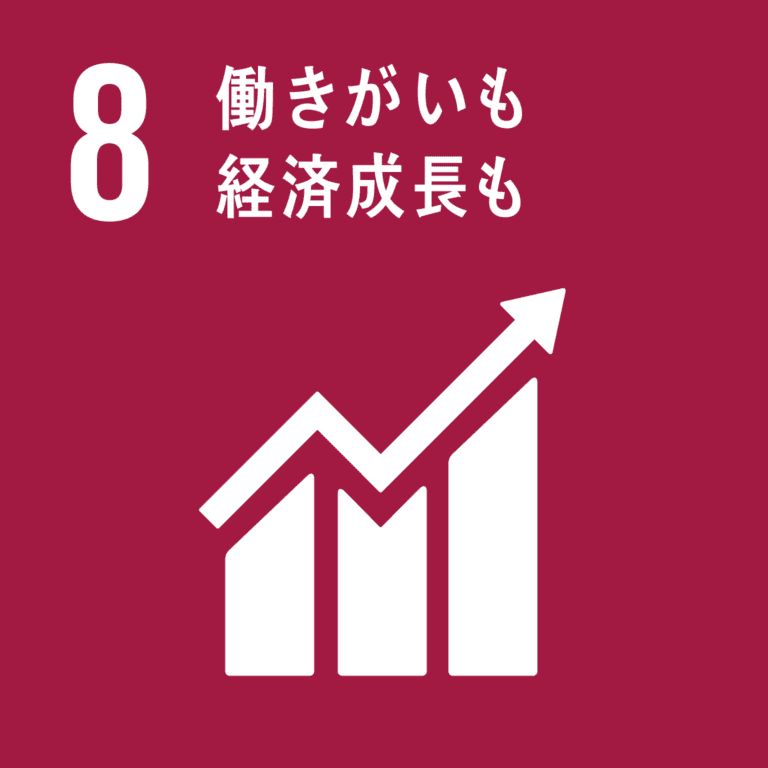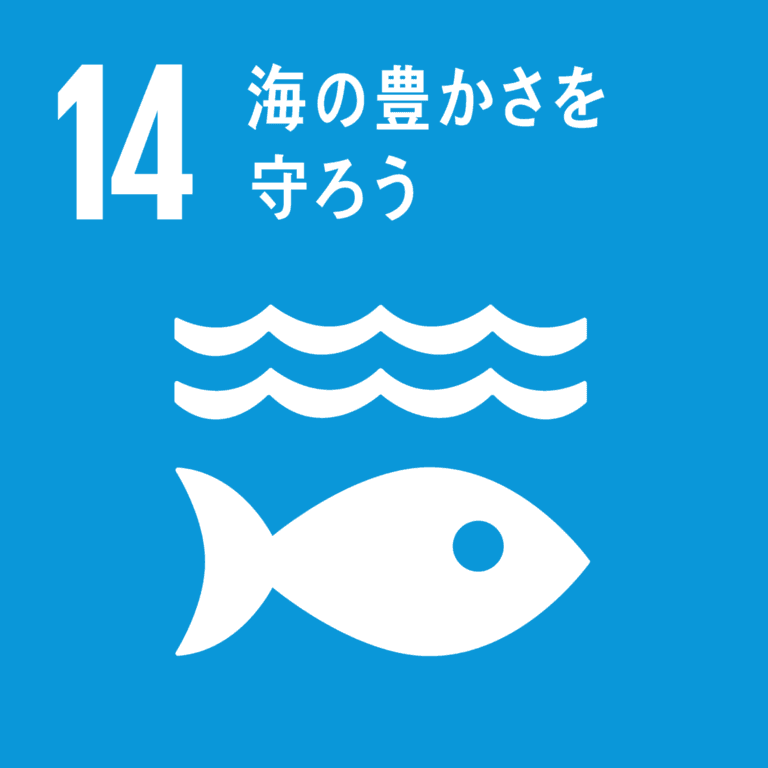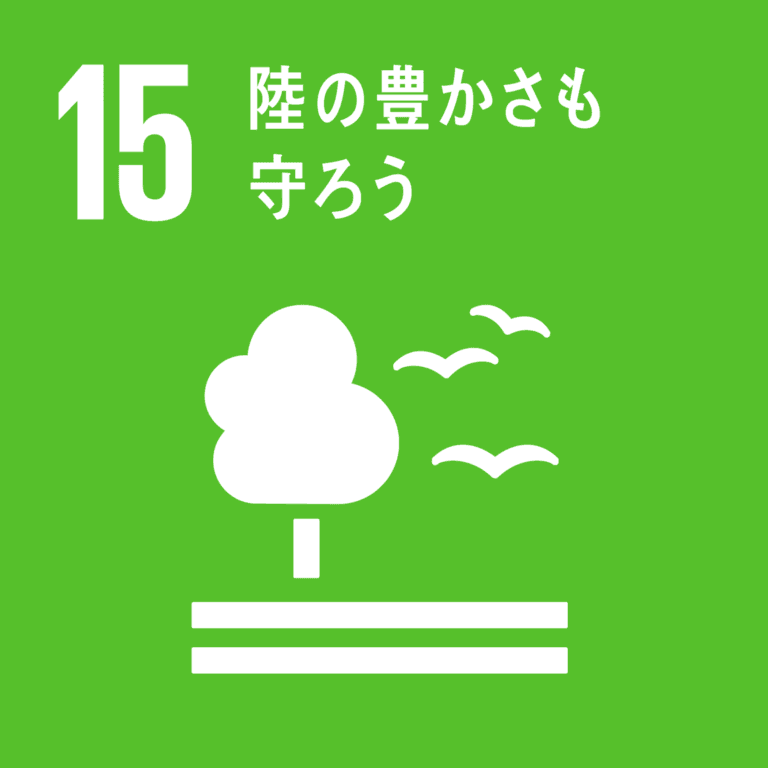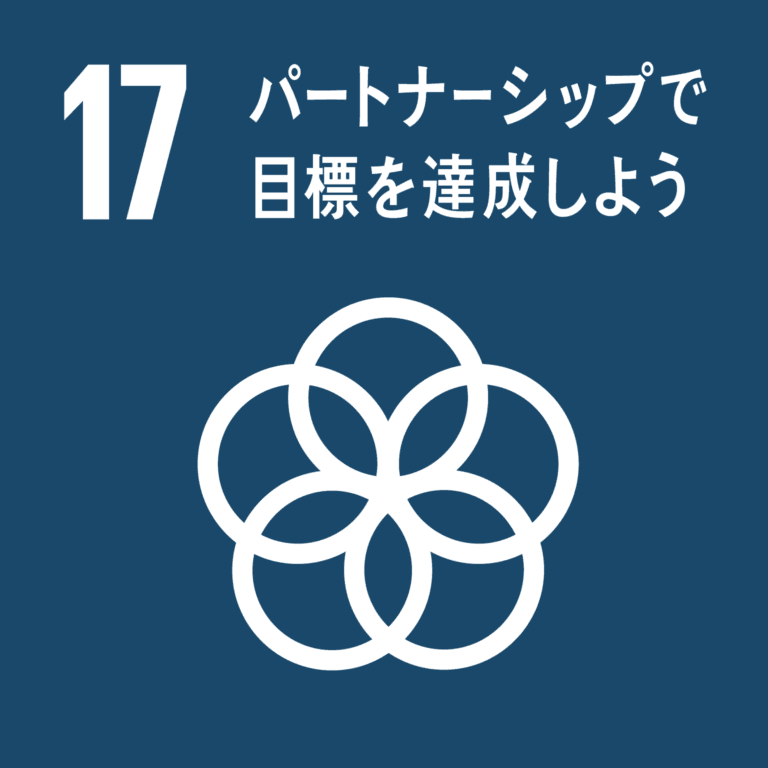小田原市は、首都圏にありながら“森里川海”がひとつらなりとなった豊かな自然環境を有しています。 その恩恵を受けながら地場産業や城下町としての長い歴史・地域文化を生み出し、人々の生活となりわいを発展させてきました。 地球温暖化などの地球規模の環境問題や、担い手不足、山林荒廃や耕作放棄地の増加など地域課題が多くある中、豊かな自然環境を次世代に残していくために活動している人々がいます。これらの活動を持続可能なものとし、すべての人々が環境と共生できる社会を目指し、次の事業に取り組んでいます。 【地域循環共生圏の構築】 地域循環共生圏の構築に向け、荒廃竹林や獣害対策など先導的な取組を創出します。あわせて、環境保全活動に係るプラットフォーム機能を担う「おだわら環境志民ネットワーク※」の機能強化等を図ります。 「※おだわら環境志民ネットワーク」 小田原の美しく豊かな自然を守り育て、「自然豊かな小田原で暮らせる喜び」を感じられる地域を未来の子どもたちに引き継ぐために、環境保全活動に取り組む団体、企業及び個人の連携協力体制を築いたり、多様な主体の連携により環境保全活動の促進へつながる循環の仕組み「地域循環共生圏」の構築に係る主たる担い手となることを目指す組織です。 平成28年3月設立。会員数83(団体35 企業11 個人37 令和6年2月29日現在) 【環境基本計画の推進(自然環境モニタリング調査)】 第3次小田原市環境基本計画(令和4年7月策定)の推進を図るとともに、適切な進捗管理を行うほか、計画を見直す際に必要な自然環境調査を行います。 【環境活動・環境学習の推進】 市民の環境意識の向上を図るため、将来を担う子どもたちに対する環境学習を行うとともに、市民による環境活動の推進を図っています。
地域の環境課題に価値を見出し、経済性を伴う地域資源としていくためには、環境課題の解決に向けた様々なアプローチが必要です。 例えば「荒廃竹林の解決」については、伐採した竹の利活用に向けた取組に関する費用や技術的支援などが必要となります。地域課題を解決し、価値を見出すためには、行政だけでは取り組むことができず、企業や市民団体など、様々な主体に関わってもらい、取り組んでいく必要があります。 少しでも多くの方に本市の状況や取組を知ってもらい、財政的支援のほか、環境課題解決につながるアイデアや連携の提案等をいただきたいと考えています。
【地域循環共生圏の構築】 本市の豊かな自然環境を次世代に継承していくために活動する環境団体、企業、個人の連携や協働を支援し、環境との共生に向けた市民活動の活性化を目指す組織である「おだわら環境志民ネットワーク」の機能強化を図ります。 【自然環境モニタリング調査の実施】 本市には、森里川海がひとつらなりとなり、その恩恵による多種多様な動植物が存在している豊かな自然環境があります。この自然環境を次世代に引き継ぐため、多様な主体が連携し環境共生型の社会の構築に向け取り組んでおり、これらの取組を一層推進していくことを目的に、自然環境等の状況を把握するため、自然環境等モニタリング調査を実施していきます。 【環境学習の推進】 市内小中学校の学習状況を踏まえた効果的な環境学習やイベント(夏休みを活用した子ども向け講座、環境学習フィールドを使用した自然学習、環境学習フェスなど)を実施します。 また、講座の講師を環境活動団体に依頼することで、実践的な学びや団体活動の推進にも繋げています。
【担い手不足・高齢化】 市内で活動する環境活動団体は、どこも高齢化や担い手の不足などの問題により、継続的に活動していくことが難しくなっており、活動を支援する必要があります。 【財政的・技術的支援】 自然環境保全の取組を持続可能なものにしていくため、関係人口の拡大や環境課題の価値化を行っていく必要があります。 そのためには、行政だけで事業を推進していくことは難しく、企業や団体など多くの多様な主体に関わってもらい、さまざまな支援をいただきたいと感じています。
小田原市は、豊かな自然環境を有し、その恩恵を受けることで人々の生活となりわいを発展させてきました。 地球温暖化などの地球規模の環境問題や、担い手不足・山林の荒廃や耕作放棄地の増加などの地域課題などに対し、豊かな自然環境を次世代に残していくために活動している人々がいます。 これらの活動を継続的なものとし、すべての人々が環境と共生できる社会を目指していくために、皆様からのご支援・ご協力をお待ちしております。