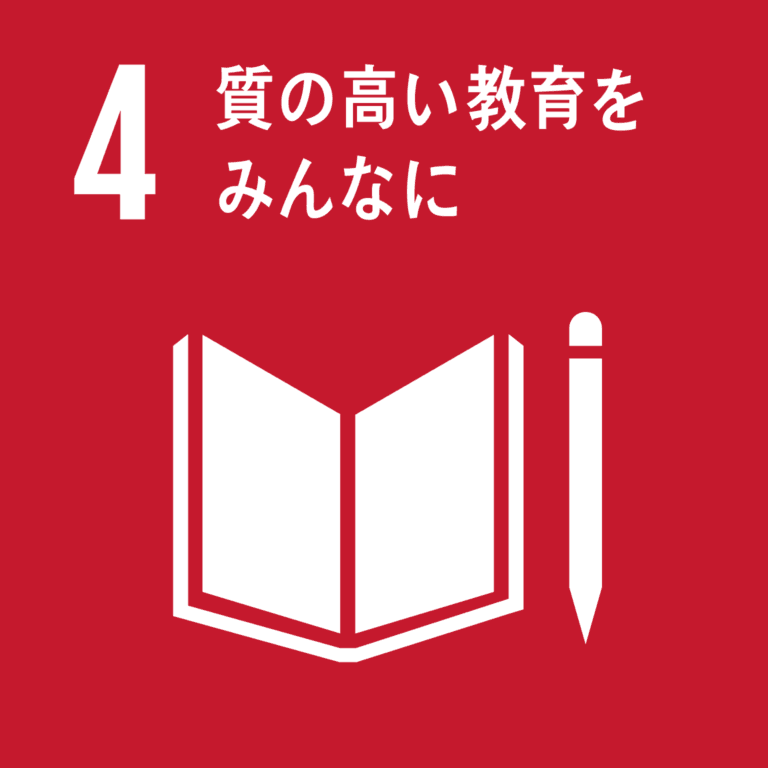『氷点』『塩狩峠』の三浦綾子の代表作『泥流地帯』が遂に映画化へ! ”全滅”と報じられた北海道の農村で、すべてを失った開拓民が「百年後の未来のために」と立ち上がり、豊かで美しい現在の上富良野を取り戻してくれました。 自然災害、紛争、ウイルス、、世界中が大きな試練に立たされる今こそ、百年前の上富良野の開拓者たちが歩んだ道、災害に立ち向かった<応災>の記憶を、企業と地域がともに未来へつなげる取り組みとして、強く推し進めています。



昨今、大規模な自然災害、ウイルス禍、国際紛争、貧困など、日本に限らず世界中の多くの人たちがさまざまな試練に立たされています。そのなかで、上富良野町は約100年前に「全滅」と報じられるほどの大規模災害から立ち上がった歴史を持っています。 大正15年の十勝岳噴火に伴う泥流災害。144名の犠牲者を出し集落をまるごと飲み込み壊滅させた災害は「融雪型泥流」という世界でも数例の極めて稀な災害類型でありましたが、その中でも同じ地域を復興させたのは史上、上富良野以外に記録がありません。 先の能登半島地震でも一部集落について、放棄は復興かという選択が迫られていました。上富良野、当時は村でしたが、まさに放棄か復興か、村を二分する大論争の果てに、重機もない時代に人力での復興という茨の道を選びました。 そして見事に復興を成し遂げ、名もない開拓者たちが100年、200年先の未来をみすえ「豊かで美しいふるさと」を取り戻してくれたという経験があります。 これは100年後、現代を生きる私たちに多くのヒントを与えてくれる歴史であると考えています。 上富良野は活火山を擁しており、自然の恵みだけでなく脅威とともに歩んできた町です。 これまでの教訓から防災と減災、備える心と大切なものを護る知恵を育んでまいりましたが、この奇跡の復興からは「応災」、つまり未曾有の災害、大きな試練に向き合い、前に進んでいく大きな力を得ました。未来を見据えて立ち向かった開拓者魂を受け継いでいます。 これは日本のみならず世界に伝えたい、そして誇りたい上富良野のレガシーでもあるのです。
「文学」という形でそのレガシーを繋いでくれたのが三浦綾子の小説「泥流地帯」と「続泥流地帯」です。 上富良野の開拓者に課せられた試練、「なぜ罪なき人に災が」、そして復興、「なぜ開拓者たちが絶望の淵にありながら立ち上がり、前に進めたのか。これが大きなテーマとなり、「応災」を実践した開拓者たちが持っていた、「諦めない心」やリーダーシップなど、まさに「根性」などと表される、数値化できない非認知能力の正体に切り込む作品です。 上富良野町がなぜこの作品の映画化に取り組みたいか。大きな動機としては二つあります。 この作品が描く試練、復興の軌跡から、現代にもたらされる大きなメッセージを世界中にお届けしたいということ、そしてこれはシンプルに「町民の夢」の実現です。 緻密な取材で当時の上富良野の歴史、文化、風俗にいたるまで国名に描かれた、「郷土史」とまでいわれるこの作品。発表から半世紀、映画化は町民の悲願でもありました。 今度は私たちが100年後の未来にこの軌跡をつないでいくこと、そして半世紀に及ぶ町民の夢の実現を目指し、取り組みを進めています。 足掛け9年となるプロジェクトですが、その間町一丸となった思いは連綿と受け継がれておりまして、いまも町中に映画化を願う思いが溢れています。
これまで製作者との協定が事業撤退などを理由とした二度にわたる解消などもあり、原作さながらの試練に立たされてきましたが、2017年から途絶えることなくプロジェクトが続いていることは、上富良野の歴史はもとより原作小説で描かれた諦めない心を町民が共有していることが大きな要因であると考えています。 そして今般、三度目の正直となる取り組みが身を結ぼうとしています。 杉咲花さん主演の「パーフェクトワールド 君といた奇跡」の柴山健次監督が名乗りをあげ、企画協力としてアカデミー賞外国語映画賞「おくりびと」の映画監督、滝田洋二郎氏が企画原案に携わっていただけることとなりました。
そこで企業の皆様にお願いしたいこと、協働の取り組みのご提案です。 上富良野町は、地域と企業の皆様で一緒にこの映画を作り上げたい、そして100年前の開拓者たちから脈々と受け継がれてきたメッセージを、企業の皆様と一緒に未来に繋ぐ取り組みをしたい、という大きな願いを持っています。 ご参画いただくことで、全国公開映画のプロモーションにて社名の露出、エンドロール掲載など、企業PRだけでなく、防災・減災・応災の地域協働、CSR活動の一環として活用いただけるものと確信しています。 最大9割の税優遇を伴う企業版ふるさと納税を、ぜひ『泥流地帯』の実写映画化での活用をご検討いただけないでしょうか。 心より、お待ちしております。