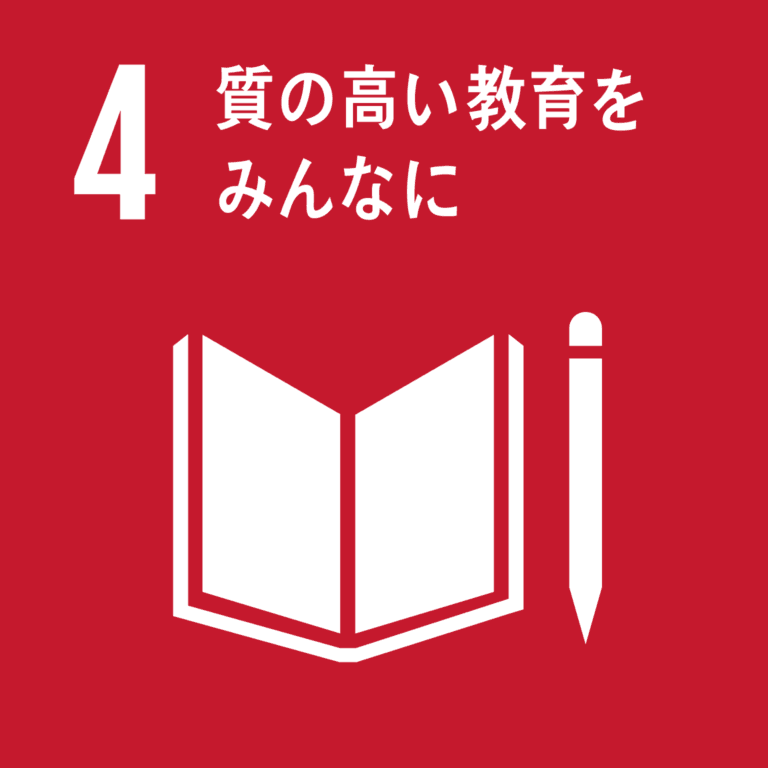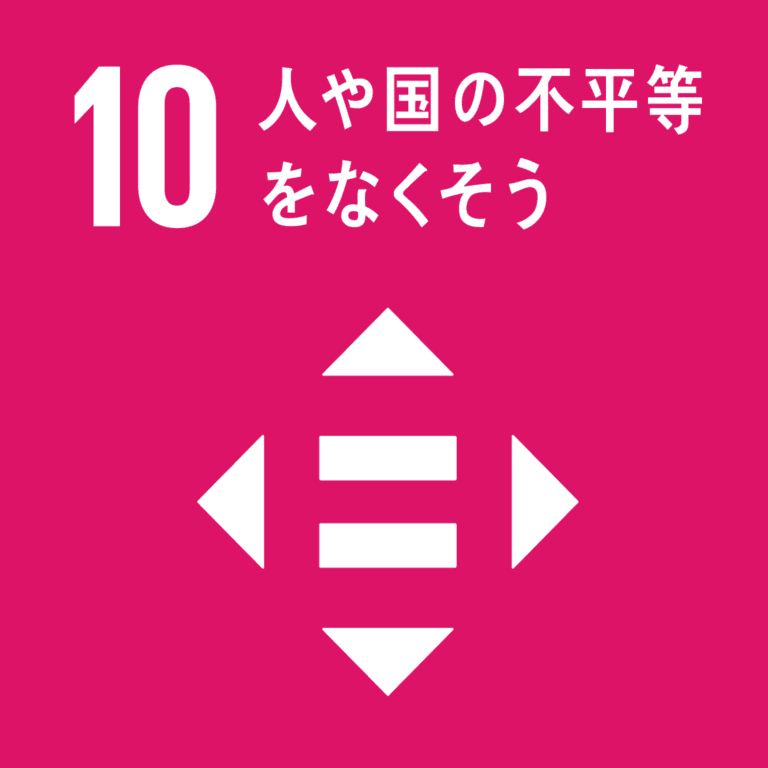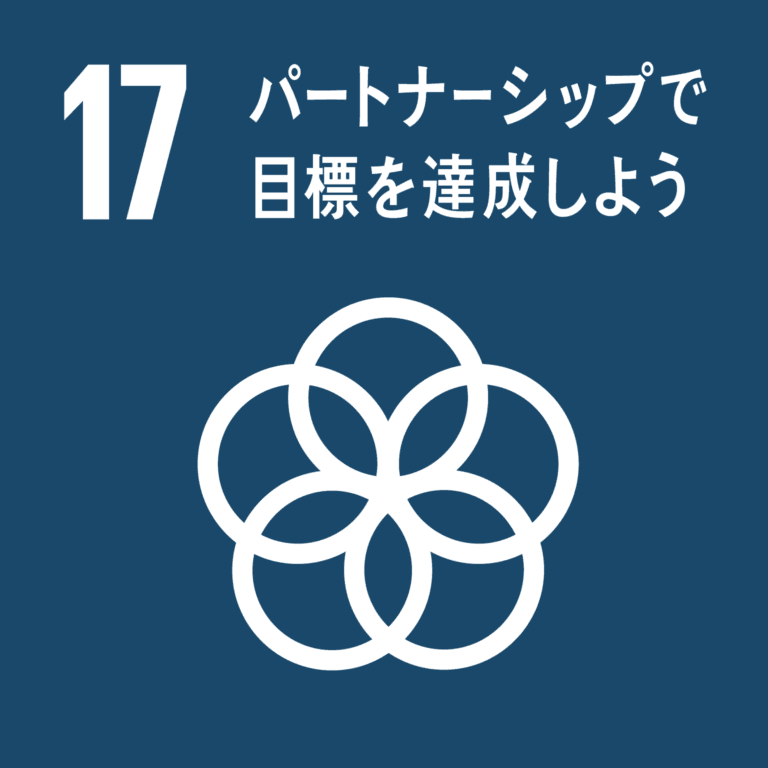うきは市では、市内の小・中学校に1人1台タブレット端末を整備し、充実した環境のもと、世界で活躍できる人材を育てます。加えて必修化されたプログラミング学習への取組みやデジタル教科書の導入、ICT支援員やデジタル人材の招聘を積極的に進め、更なる教育環境の充実を図ります。 当市では、近年、移住者が増加傾向にあるものの、20~30代を中心とした子育て世代は、より良い環境を求めて隣接する久留米市や福岡市に流出する状況が続いています。全国的な傾向として、東京への一極集中が加速している状況に歯止めをかけるには、地域の文化資本を積極的に活用し、子育て世代の定着を図る必要があると考えます。そこで当市では、タブレット端末による学習やプログラミング教育といった先進的な学習方法を導入。学力向上に加え、子どもの思考力や感性、「生きる力」を磨く教育環境を整え、次代を担う人材の育成を行っています。
うきは市の子どもたちは素朴で優しい半面、のんびりとした土地柄ゆえか、野心や向上心に乏しく、勉強が苦手でも「家業の農業を継げばいいや」と楽観的に構えている傾向があります。急速に変化している現代において、しなやかに生き抜く力を身に付け、世界で活躍する人材を育てていくためには、チャレンジ精神旺盛な人たちとのパートナーシップが必要と考えています。 うきは市では20~30代を中心とした子育て世代の流出に加え、10代後半~20代前半の若年層の流出も近年増加しています。その理由の一つに、高校を卒業した若者が進学のために市外へ転居することが挙げられます。彼らが学業を修めたのちに帰ってきたくなる、あるいは当市の魅力を発信したくなるようにするには、子育て環境の整備と教育の充実が重要な課題となっています。
市内すべての小・中学校がICT優良校に認定されており、児童生徒1人1台のタブレット端末の配置やデジタル教科書導入など、先進的な教育環境を整備しています。タブレット端末を活用したプログラミング教育では、ゲーム感覚で楽しみながらプログラミングを学べるソフトを導入し、技術だけではなく論理的な思考力も養っています。 また、ICT支援員やデジタル人材の招聘による指導力の向上や、日本人ALT(外国語指導助手)の配置による英語教育の拡充にも取り組んでいます。さらに幼少期から感性を磨き、豊かな心を育てるために、音感教育の導入や外国との異文化交流を実施し、将来は世界で活躍できる人材を育成していきます。そのほか、公共施設に高校生ボランティアが小学生に勉強を教える「寺子屋」を設置したり、子どもたちの生きる力を磨く自然体験活動を催したりと、さまざまな観点から子どもたちの成長をサポートしています。
うきは市の人口は3万人を下回っており、市外(特に久留米市)への流出に歯止めがかかっていません。そこで外部活力と協働・連携し、教育に必要な費用や講師の派遣などについてアイデアをいただきながら、子どもたちが成長していく過程を一緒に見守っていきたいと考えています。 本事業は始動してから約3年経過しました。目に見える結果が出にくい取組みではありますが、小学校の学力は全国平均を上回り、中学校も間もなく上回る見込みなど、子どもたちの学力にも少しずつ変化が表れて始めています。新しい時代を担う子どもたちを育むことは、当市だけでなく日本全体、ひいては世界の未来にもつながっています。子育てや教育、次世代の育成に興味を持ち、本プロジェクトにご賛同いただける企業を募集しています。
うきは市は、年間を通してさまざまなフルーツが栽培されている全国屈指のフルーツ王国です。近年は、フルーツを使ったスイーツショップや、農業生産者が営むカフェなど6次産業も増えています。その一方で大部分の農家は後継者不足に悩まされ、次代の担い手が経営論を学ぶ機会もないまま高齢化が進んでいます。農業産出額を見ても2014年には89億円でしたが、2017年には84億円に、総農家数も1990年の3,444戸から2015年には1,377戸にそれぞれ減少しています。このような地域産業の衰退を食い止めるには、若い世代の活躍が絶対に欠かせません。 皆様には、地元育ちの若者たちが新しい価値観で魅力あるまちづくりに取り組めるよう、応援していただけると心強いです。また、子どもたちが夢を持って、より広い世界へと羽ばたいていけるよう、ご支援いただけるとうれしく思います。
市内すべての小・中学校の児童生徒に1人1台のタブレット端末を導入中です。これまでに500台配置され、2021年2月に導入が完了します。 2020年は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、オンライン教育やリモート授業の需要が高まり、文部科学省が全国の小・中学校に1人1台タブレット端末を配布する計画を始めました。うきは市ではそれに先駆けて導入に着手していたため、有効的な活用が進んでいます。 また、2016年度から進めている教師の指導力を高める研修や、市内の幼稚園・保育園での音感教育・英語教育等を拡充するなど、次代を見据えた人材育成にも引き続き取り組んでいきます。