「地域のストーリーを、読者の自分ごとに」
企業版ふるさと納税に応用する、人を動かすストーリーのつくり方
2022-03-18 08:00:00
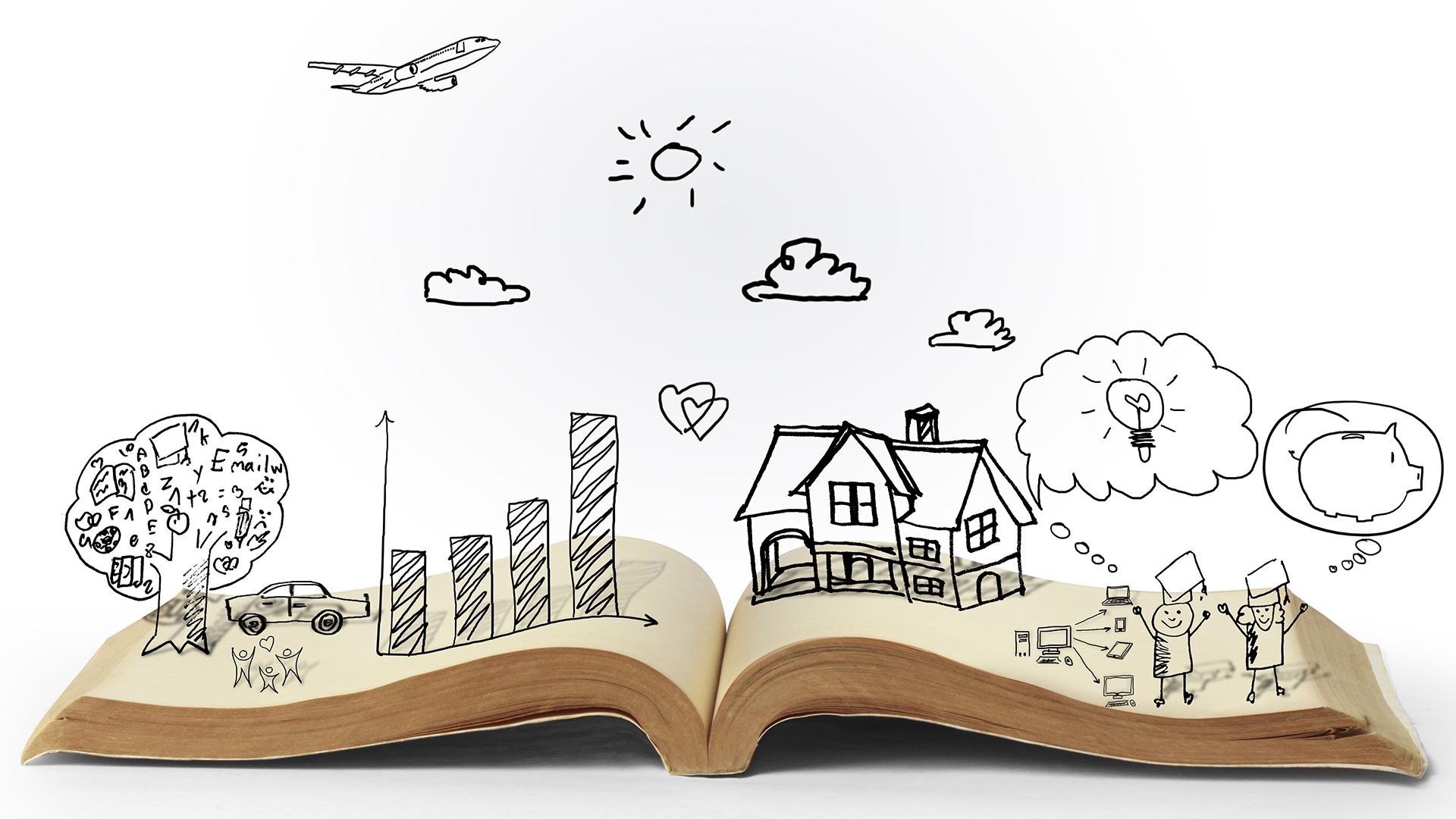
企業版ふるさと納税のプロジェクトの魅力を知ってもらい、寄付につなげるためには「多くの人に認知され、信頼され、共感される情報発信」が必要不可欠です。そのために取り入れたいのが「ストーリー」の要素です。感情が揺さぶられるようなストーリーに出合い、「このストーリーに自分も加わりたい」と思った時に、プロジェクトが読者の「自分ごと」になり、読者の行動が変わっていきます。では、そのような人の心を動かすストーリーはどのようにつくることができるのでしょうか。本記事では、企業版ふるさと納税のプロジェクトを効果的に伝えるストーリーづくり、ストーリー性のある文章の書き方のノウハウについて解説します。
「ストーリー」とは何か。売れる商品や人を動かすプロジェクトにはストーリーがある
ストーリーとは、「小説や演劇、映画などの創作物などの筋書のこと」を指します。現実世界の話題でも、ストーリーのような伝え方ができるかどうかで、受け止める側の印象は大きく変わってきます。
文章にストーリー性をもたせるためには、情報を脈絡なく、羅列的に配置してはいけません。情報をテーマと筋道に沿って、構成・配置していくことで、初めて情報はストーリーとなるのです。例えば、「本を買った。友人に出会った。喫茶店に行った」というのは脈絡のない情報の羅列ですが、「英語の本を買いに行った。書店で偶然、帰国子女の友人に出会った。その後、喫茶店で友人から英語のレクチャーを受けた」というように情報をテーマに沿って抽出し、再構成・最配置すると、それは筋道のあるストーリーとして人に認識されます。
売れる商品や、多くの人を動かすプロジェクトの背景には、必ずストーリー性のある情報発信があります。商品のスペックや効能をただ箇条書きで伝えても、その魅力は伝わりません。しかし、その商品のスペックや効能に加え、使うことによるメリット、どんな変化を社会に起こそうとしているのかを、脈絡ある一連のストーリーとして伝えることで、消費者に商品の価値をわかりやすく伝えることができるのです。企業版ふるさと納税のプロジェクトにおいても、ストーリー性のある情報発信は必要不可欠であるといえるでしょう。
文章にストーリー性をもたせるためには、情報を脈絡なく、羅列的に配置してはいけません。情報をテーマと筋道に沿って、構成・配置していくことで、初めて情報はストーリーとなるのです。例えば、「本を買った。友人に出会った。喫茶店に行った」というのは脈絡のない情報の羅列ですが、「英語の本を買いに行った。書店で偶然、帰国子女の友人に出会った。その後、喫茶店で友人から英語のレクチャーを受けた」というように情報をテーマに沿って抽出し、再構成・最配置すると、それは筋道のあるストーリーとして人に認識されます。
売れる商品や、多くの人を動かすプロジェクトの背景には、必ずストーリー性のある情報発信があります。商品のスペックや効能をただ箇条書きで伝えても、その魅力は伝わりません。しかし、その商品のスペックや効能に加え、使うことによるメリット、どんな変化を社会に起こそうとしているのかを、脈絡ある一連のストーリーとして伝えることで、消費者に商品の価値をわかりやすく伝えることができるのです。企業版ふるさと納税のプロジェクトにおいても、ストーリー性のある情報発信は必要不可欠であるといえるでしょう。
ストーリーづくりの基本は、「テーマ決め」と「始まりと終わりの設定」
では、筋道だったストーリーはどのようにつくれば良いのでしょうか。
いざ、「ストーリーをつくる」となると難しそうに感じますが、複雑なプロセスが必要なわけではありません。ストーリーづくりで重要なことは二つです。一つは、テーマが定まっていること。もう一つは、テーマに従った「始まり(スタート)」と「終わり(ゴール)」が明確になっていることです。決めたテーマに従って、「何故、それをしたいと思ったのか」という原点と、「実現したい未来や起こしたい変化」の2つの点を設定し、それらを線でつなぐことで、ストーリーの大枠ができあがります。その線の上に、テーマに沿って情報を構成・配置していくことで、人に伝わる筋道だったストーリーができあがるのです。そして、このストーリーに共感し、「自分も加わりたい」と思った時に、人の行動変容が起こります。
もう迷わない! ストーリー性のある文章をつくる手順とポイント
ストーリーづくりは手順を細分化して整理することで、より分かりやすくなります。以下に、SNSや広報紙などを通じた市民向けの情報発信において、ストーリー性のある文章で企業版ふるさと納税のプロジェクトや地域活動を紹介するための有効な手順と、ポイントについてまとめましたので、ご紹介します。
①情報を整理し、重要だと感じたポイント、自分の心が動くポイントを抜き出す
文章を書こうとする際に、「頭の中が散らかった部屋のように散乱している。何をどういう順番で伝えたら良いのかわからない」という状態に陥った経験はないでしょうか。そういった場合に有効なのは、メモや資料、録音の文字起こしなどを並べてみて、自分が「これは重要だ」「心が動いた」と感じたポイントを抜き出すことです。自分が感動したポイントにこそ、他者の心を動かすヒントがあるからです。
②感動したポイントからテーマを一つに絞り、ストーリーの「見出し」を設定する
感動したポイント、重要そうなポイントをいくつか抜き出したら、そのなかから「最も伝えるべきことは何か」を決めて、テーマを一つに絞ります。ストーリーづくりにおいて重要なことは、テーマ、つまり話の軸が一つに定まっていることです。複数のテーマが入り混じっている話は、読み手が混乱してしまうからです。テーマが決まったら、ストーリー(文章)の「見出し(タイトル)」を考えてみましょう。テーマを見出しとして言語化することで、話の軸をよりクリアにすることができます。
③設定したテーマに従って、スタートとゴールを設定した上で情報を再構成する
テーマが設定できたら、そのテーマに従って、「そのプロジェクトを始めようとした理由や背景(スタート)」と「そのプロジェクトを通じて実現したいこと(ゴール)」を書き出します。そうすることでストーリーの大筋が見えてきます。その上で、プロジェクトを進める上でのやりがい、現在課題になっていること、関係者の声などの要素を書き出し、文章全体の構成をつくります。ここで重要なことは、文章を書き始める前に構成をつくることです。構成の時点で筋道が整っていれば、文章もスムーズに書くことができるでしょう。
④段落同士、文と文の接続に論理的な飛躍がないかを注意して構成・文章をつくる
文章の構成のパターンは、「起承転結」「三段構成(序論→本論→結論)」「頭括構成(結論と要旨を先に提示する)」など、様々な型があります。状況や発信する媒体、文字数の制限に応じて使い分けることが望ましいですが、いずれの構成においても、スタートとゴールが明確になっていること、段落同士、文と文の接続がスムーズになっていること(論理的な飛躍がないこと)を意識しましょう。文や段落に論理的な飛躍があると、文章からストーリー性が損なわれ、読み手が混乱する原因になります。
⑤ゴールの時点で社会・未来にどのような価値をもたらすのかを詳細に描く
「自分も加わりたい」と読み手が感じるストーリーには、将来どのようなことが起こるのか、プロジェクトを通じて地域や社会がどのように変化するのか、そのことによって、読み手にどのようなメリットがもたらされるのか、が明確に描かれています。自分がそのプロジェクトに参画・協力することで、「このストーリーが現実のものになる(自分にとっても何らかのメリットがある)」と読み手が確信できれば、読み手はストーリーを他人ごとではなく、自分に関係のある事柄として捉えられるようになるのです。
地域のストーリーを読者の自分ごとにできるかどうかが鍵
企業版ふるさと納税のプロジェクトは、プロジェクトができあがった段階では、それを届けたい人にとって「他人ごと」です。その「他人ごと」を読者の「自分ごと」にしていくためには、プロジェクトをストーリー性のある情報として発信して、共感されることが必要不可欠です。今回は、ストーリー性のある文章のつくり方についてご紹介しました。日ごろの業務や、情報発信にご活用いただければ幸いです。
(イーストタイムズ 畠山智行)
(イーストタイムズ 畠山智行)


